
海外から商品や部品を購入する、あるいは自社商品を輸出する場合、必ず直面するのが「不具合」「欠陥」などのトラブルです。
不具合、欠陥は英語で何と言う?
機能に欠陥がある場合は”defect“と言います。
出荷検査などで出荷基準から外れたものや、返品された不良品などは”defective product“です。
一方、failureにも「不具合」という意味がありますが、どちらかというと機械の故障、障害、といった意味合いが強いです。
流れで言うと、
です。
何らかの障害(fault)によって異常(error)が引き起こされて、その結果、故障(failure, malfunction)するわけです。
機能、仕様に欠陥がある場合など指す。 単純に障害が起きて故障した、というより機種全体に波及するような問題を含んでいる感じ。
defective product(不良品)
・failure
故障、障害を指す。装置単体での故障の場合はfailure。(類:malfunction)
engine failure(エンジン故障)…エンジン設計の問題では無く、個体的な故障。
ただし、どちらの場合でも原因が仕様や部品自体の問題に行きつくと、問題は機種全体に及ぶのでdefect(欠陥)で表現される場合もあります。
口語で「故障した」「壊れた」「動かない」という場合は”It doesn’t work.“ですね。何にでも使えます。
不具合の原因はcause, 真の原因はroot cause
当然、不良品や故障品が発生すると原因追及が必要です。
不具合や問題の原因は英語で”cause”。because(なぜなら)はcauseの派生語ですね。
その「原因」を引き起こす「真の原因」のことを”root cause”と言います。(”root”は木の根のこと)
causeとroot causeの違いですが、例えば、とあるメーカー製の冷蔵庫が突然冷えなくなったとクレームがあったとしましょう。
原因を調べてみると、温度センサの取付け方が甘く基盤から外れかかっていたために温度センサが正しく働いていないことが判りました。
そのため、冷蔵庫が冷えなくなったのは「温度センサの取付方に問題があった」ことが原因です。(一次原因)
しかしそこから更に踏み込んで「なぜ、温度センサの取付方に問題が発生したのか?」を追求していきます。
調査してみたところ「温度センサの基盤への取付には細かいハンダ付け作業と調整が必要で、作業者の技量によって取付け作業にバラツキがでる」ことがわかりました。
これが真の原因=root causeです。
実際のメーカーでは更に踏み込んで「なぜ作業者の技量にバラツキが出るのか?」とか「非熟練作業者でも容易に取付けできるような冶具、ツールは無かったのか?」など追求していきます。
問題の修正はfix
“原因”や”真の原因”が分かれば、後は不具合を修正します。
修正や修理は”fix”や”repair”です。
“fix”は修理でも修正でも何にでも使える便利な言葉です。アメリカでは何でも”fix”ですね。
“repair”はどちらかというと破損した部分を直すとか、剥がれたところを元に戻す、というように「元の状態に戻す」というニュアンスがあります。
ただこれもあまり明確な差異は無く、アメリカではぶつけて凹んだ車のドアを直すのも”fix”です。
プログラムに不具合があってそれを修正するのも”fix”です。ソフトウェアや電気回路は「元の状態に戻す」というのとは少し意味合いが違うので”repair”とは言いません。
問題の修正に時間がかかる場合はworkaroundを出す
問題は確認した。原因、真の原因も突き止めた。問題の解決方法もわかったが、修正~動作確認~リリースまでには少し時間がかかりそうだ、というときは、市場のユーザーに対して”workaround”(応急措置の方法)を出すのが一般的です。
“workaround”は日本語で「応急措置」「暫定措置」と訳されます。
電子機器には多くのICチップが使われていますが、その回路の集積度合が大きすぎるために全てのテストパターンを網羅するのが難しく、チップがリリースされた後に不具合が発覚することが度々あります。
その不具合情報のことを「エラッタ(errata)」と呼びます。
そのエラッタには、不具合の症状(symptom)、原因(cause)、回避方法(workaround)が記載されていますが、時々、”workaround: none”(暫定対処:無し)という非情なエラッタを見かけることがあります。
さすがに日本の半導体メーカーでこういうことを言うところはありませんが、海外のチップベンダだと割とよく見かけます。
さすがにその時は部品採用を決めた自分を恨みますね。
英文でメールを書くのに時間がかかり過ぎる?
海外企業に送るメールを書くのに1時間もかかったり、ビデオ会議で「言いたいことはわかっているのに、それが英語でうまく表現できない!」ってことありませんか?
「書きたいことが英語で表現できない」「言いたいことが英語にできない」のは、英語の定型文のストックが全然足りないからなんです。
メールや会議の質疑応答で使う文章って、実はほとんどが決まりきった文章で事足りてしまいます。
多くの人は”May I help you?”(お手伝いしましょうか?)を、「えーと、動詞がhelpで助動詞が…」なんて考えませんよね。「手伝いましょうか?=May I help you?」と丸ごと覚えているはずです。
つまりこういった定型文の引き出しが多ければ多いほど、英文メールの作成時間が短くなり会議で聞きたいことをパっといえる瞬発力に繋がります。
こうした日常会話の定型英文を効率よくまとめたのが7+Englishです。

私も以前は自力で英文を考えてメール書いていたので、たった数行の英文メールを書くのに2~30分もかかっていたりしましたが、英文の定形パターンを身に着けてからは、頭で考えた文章がスラスラと英語化できるようになりました。
英文メールの作成に時間が掛かっている人、ビデオ会議で言葉がうまく出てこない人は是非試してみてください。
>>【7+English】~60日完全記憶英会話~ 公式ページ
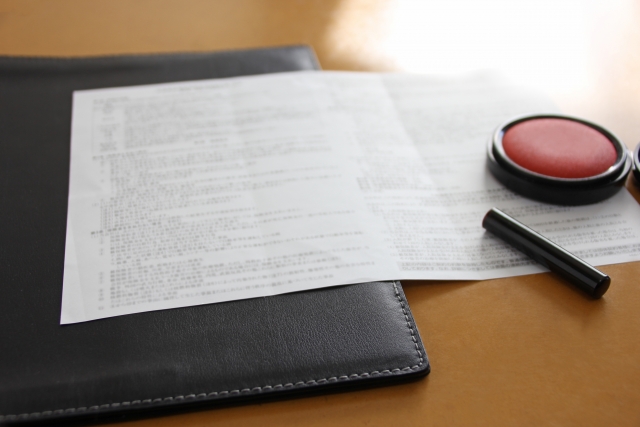

コメント