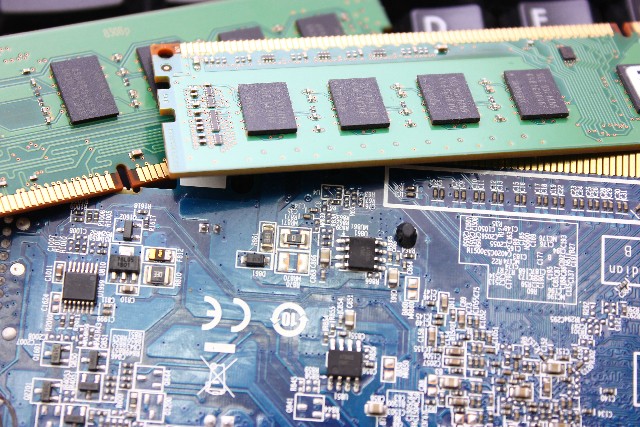
“部品メーカー”とか”自動車メーカー”とか、一般的に製造元のことを日本では”メーカー”と呼びますよね。
電機業界で言えば、日立、東芝、ソニー、パナソニックなんかは最終製品を作る”メーカー”ですし、村田製作所やROHMなどは部品”メーカー”です。もちろん、語源は”maker”(作る人)に由来します。
ところで、英文メールを書くとき”メーカー”をそのまま”maker”にしてませんか?
これ、間違いではありませんが、もっと英語っぽい言い方があります。
日本語の「メーカー」は英語では”manufacturer”
例えば、
と聞く場合、
・Who is the maker of this parts?
でも全然通じます。
これらはよく使われる言い方ですが、この言い方だと「この炊飯器ってどこのメーカーだっけ?」みたいな感じに一般の人が聞いてるような感じです。
そこで、ビジネスや開発・設計現場で使う場合は、
・What company manufactured of that part?
・What is the name of this part manufacturer?
のようにmanufacturer(製造者)を使うのが一般的です。
日本語で「メーカーに勤めている」というと「大企業に勤めている」という意味も含まれますが、”maker”自体には「大規模」という意味はありません。
なので製品を作っていれば個人でも大企業でも”maker”です。しかし製品を作っている個人を”manufacturer”とは言いません。”manufacture”には「(機械で大量に作る)製造」という意味がありますので、”manufacturer”は「大量に製造する」製造業者、という意味になります。
ただし例外として、自動車メーカーのことは”automaker”といいますね。auto + makerでautomaker。
“car maker”でも通じないことはありませんが、なんとなく個人が小さな工場で受注生産でもやっているようなイメージがあります。
他には”automobile manufacturer”、”motor manufacturer”というような言い方もあります。
辞書を鵜呑みにしない
“maker”を辞書で引くと、大体「製作者、製造者、メーカー」と書かれているので、英語初心者は「メーカー=maker」で合ってるんだ、と思ってしまいます。しかもそれが完全に間違っているわけじゃないのが歯がゆいところ。
私も当初は英文メールで「メーカー」の意味で”maker”をよく使っていましたが、ネイティブとのやりとりが増えていくうちに日本語の「メーカー」は”manufacturer”のほうが近いのでは?と思うようになってきました。
このように、日本語と英語で意味がズレている単語はたくさんあります。
しかし辞書は単語の意味については書いてありますが、その単語があなたが使いたい意味や状況にフィットしているかどうかまでは書いてありません。
そのため、辞書で意味を確かめたらまずは使ってみる、意味が通じればまずはよしとしてそのまま使ってみましょう。
英語でのコミュニケーションを通じて、自分の単語の使い方が正しいかどうか「感じる」のです。
そして、ネイティブや自分よりも英語がうまい人の表現を盗んで真似ることで、単語の正しい使い方がどんどん身についていきます。
文章や論文を盗むと盗作になってしまいますが、表現や言い回しはいくら真似してもOKです。上手い表現はどんどん盗んで自分のモノにしちゃいましょう。


コメント