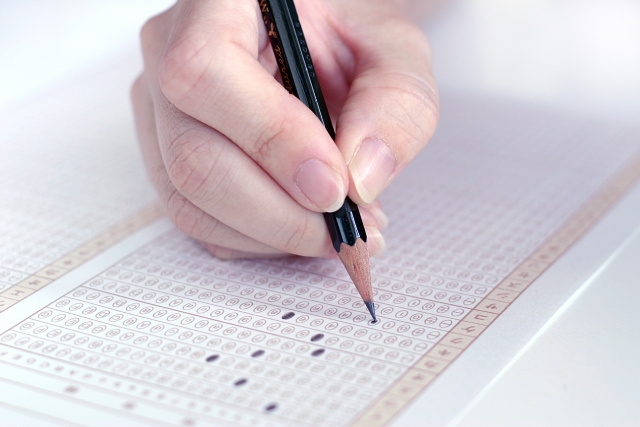
いよいよ最後のパートにして最大の難関であるPart7です。
このパートは長文読解問題で、TOEICリーディングパートの中で最も多い問題数(54問)です。
いろんな説明が書いてある文書を読み、それぞれ2~5問の問題に解答していきます。
旧形式ではPart7は48問でしたが、新形式では6問増えて54問になりました。
シングルパッセージ、ダブルパッセージ、トリプルパッセージとは?
Part7の問題にはシングルパッセージとダブルパッセージの2種類があります。
シングルパッセージとは、手紙とか広告などの長文が1つだけのものを指します。
長文の種類には
- 手紙・電子メール
- 広告、求人広告、チラシなど
- 取扱説明書や注意喚起文
- 新聞記事
- 募集、告知文など
といったものが多いです。
ダブルパッセージとは、2つの関連した長文のことです。例えば、
- 送り側の手紙やEメールとそれに対する返信
- 告知文とそれに対する質問メール
- 書籍の広告とそれに対する書評
と、2つの長文が関連をもっているものです。
更に、2016年5月のテストから3つの関連した長文のトリプルパッセージ問題が追加されました。(ダブルパッセージ、トリプルパッセージなどをマルチプルパッセージといいます)
文書が2から3つになっただけで、それらの文書の関連を問う問題が出る点ではあまり差異がありません。ただ、ダブルよりトリプルのほうが多少面倒臭いだけです。
Part7の攻略法は?
こんなこと言うと身も蓋もないですが、初心者がPart7を攻略する小手先のテクニックは…ほとんどありません。
Part7は何といっても大量の長文を短時間で読み解く読解力が求められます。ゆっくり時間を掛ければ理解出来るのに、というレベルでは試験時間内に解答出来ません。
TOEICは速く読めることも高得点の内なのです。
この「速いリーディングスピード」を身に着けるのには近道がありません。
中級者であれば、
- 英字新聞を読む
- ペーパーバックを読む
などでリーディングスピードを鍛えることが出来ますが、そもそも英語の基礎力が不足しているスコア500点台の人が英字新聞を読んでも、文法力、語彙力が不足しているのですから意味を読み取るのですら大変でしょう。
それに、英語初心者だとPart7に到達したときにはリーディングパートの試験時間(75分)の大半を使っているか、中にはPart7までたどり着けない人もいると思います。
その原因はやはり英文読解力、リーディングスピードが圧倒的に遅いからなんです。
そのため英語初心者は、ぱっと見てわからない問題はどんどん飛ばして、わかりそうな問題に時間をかけるという戦略ぐらいしかありません。
初心者のPart7対策
初心者であればまずはPart5の対策を徹底的にやってください。
Part7の対策にPart5をやるの?と思うかもしれませんが、Part5は英文法をどれだけ理解しているかを問うパートですから、Part5の正答率を上げないと、その後の長文読解に時間ばかりかかってしまいます。
どんな長文問題でも複数の文から成り立っています。一つの文は第一文型~第五文型のいずれかに必ず該当します。完了形でも仮定法でも疑問文でも必ず第一~第五文型に該当します。
そのため、長文読解を効率よくこなすには文法の理解が何よりの近道です。
長文を読みながらいちいち文型を気にするの?
「英語を理解するのにいちいち文型を気にするなんてナンセンス」「そんな暇があるならどんどん英語に触れるべきだ」という方も中にはいるでしょう。
確かに、英文法をキッチリ勉強しなくても大量のインプット(リーディング/リスニング)と大量のアウトプット(ライティング/スピーキング)をこなすことで英語力を上げることは出来ます。
しかしここで私が伝えたいのは、いかに効率良く英語を学習するか?です。
やみくもにインプット/アウトプットを繰り返すより、英文法を理解した上でインプット/アウトプットを行ったほうが、より少ない時間で同じレベルに到達できるので学習効率が良いのです。
初心者が長文を読んでいて困るときは、単語の意味はほとんど分かっているのに、文章全体の意味がわからない、というときではないでしょうか。
この原因は、
- イディオムの意味がわかっていない
- 文の構造がわからない(文型がわからない)
のいずれかです。
最初は「え~と、これは目的語でこれは補語だから…」と頭で考えながら読み解いていきますが、これを繰り返していくうちに頭の中に文型のパターンが染みついてきて、そのうちに文型を意識せずに読み解けるようになってきます。
つまり、Part5対策を行うことはそのままPart6, Part7対策になるのです。
中級者以上のPart7対策
Part7は文章量が多いパートです。時間内に頭から読み切れる実力があるのがベストですが、頭から必死に解答するものの時間が足りず後の問題はマークシートを塗り絵してしまう、というのではもったいない話です。
現時点でそこまでの実力が備わっていない場合、目指すべきは「Part7の解ける問題、易しい問題は取り逃さない」です。
Part7の問題を見て「簡単そうな問題か、難しそうな問題か」を見分けて、難しそうであればさっさと次に進みましょう。
最後まで一巡したところで再度Part7の初めに戻り、飛ばした問題の中から再度「自分が解けそうな問題、難しそうな問題」を見分けて解答していきます。このとき、難しそうであったら飛ばして次に進んでも構いません。
そして最後に残っている問題を制限時間いっぱいをかけて解答し、最後どうしても解答出来ない問題は塗り絵で解答します。
こうすることで、少なくとも現時点の実力で解ける問題を取りこぼすことが無くなります。

コメント